注:このページの全ての動画において日本語字幕をご利用いただけます。
字幕の表示方法はこちら
「選択の余地はなかった。あの状況では、議論もなしにただ去るのみだけだったよ。」
不確実性、残酷な皮肉、サバイバル、忍耐、変化、適応 – シリアを後にしたヤセルの経験は、彼の人生の進路を永久に変える要因によって強調されました。ダマスカス大学で英文学を専攻し、サッカーに熱中していた気楽な生活とは一転して、爆撃で家を失い、生きる術を失い、家族を養うために自分自身や個人的な目標を忘れなければならなくなったのです。ヤセルには、自分と家族が生きていくことを確実にするために、これまで知っていた唯一の生活を捨てるという選択肢しか残されていませんでした。

1. エジプトでの経験
故郷を追われることは、誰もが望まない運命です。しかし、家が灰塵と化した今、ヤセルと彼の家族はシリアでの快適な生活から逃れるしかありませんでした。2日以内に必要な書類をすべて集め、大切な荷物をまとめ、新しい生活を求めてエジプトに向かう以外に選択肢はなかったのです。ダマスカスを後にし国境を超えることを希望する人向けのSUVの乗り合いサービスタクシーを予約してもらい、エジプトへ飛んだレバノンまで向かいました。
ヤセルは、自ら選んだわけでもない新たな人生に突き落とされ、難民となったのです。


エジプトに到着すると、シリアにいたヤセルの友人のエジプト人の知人が家を貸してくれました。しかし、21歳という年齢では、経済的に安定した両親が必要なものや欲しいものをすべて与えてくれるような生活しか知らなかったので、放課後はどの友達と一緒にサッカーをしに行くのか、母親は何時に仕事から帰ってくるのか、英文学の宿題はどの本を読めばいいのかというようなことだけを心配していたので、ここまで急激な変化は初めてでした。
ダマスカスで家族や親戚と住んでいた大きな集合住宅から、ヤセルはエジプトのスラム街に追いやられてしまいました。その汚さは、ヤセルがこれまで見てきたものとは比べものにならないほどでした。


ライフスタイルが180度変わるような生活は耐え難いものでした。ヤセルと彼の家族は3日間この家に滞在しようとしましたが、あまりの居住性の悪さに、耐え忍ぶことはできませんでした。ゴミ、犬、ゴキブリに日常生活を妨害され、どんな犠牲を払ってでもこの場所から引っ越す決意を固めたのです。
1.1. 「ここから出して。どんな値段でも、どんなお金でもいい。」
ヤセルと彼の家族はカイロのマディナティに引っ越すことを決めまし。新しいエリアであるマディナティについて、ヤセルは「ちょっと高級な感じで物価も高いけど、警備が厳重で、整然されていたよ。どの建物にも警備員がいて、閉鎖的な街といった感じ。スーパーマーケットが2軒あるだけで、移動は小さなバスになるんだけど、安全だから引っ越したんだ。」と話します。ヤセルの家が爆撃を受けて彼と家族の命が危険にさらされたのはほんの数日前のことだったので、安心感が最優先事項だったのです。
1.2. 「あのような状況に置かれた後、最低限必要なのは、安全で清潔な場所に住むことだった。」


マディナティ地区は当初住んでいたエジプトの 「スラム街 」とは物理的にかなり違う上に、家賃も月7,000英ポンド(2023年8月現在33,000円)以上と大きな差がありました。しかし、ヤセルと彼の家族は経済的に苦労していたわけではありません。難民というと、キャンプやボートで命からがら生活している人たちという固定観念がありますが、こうした状況は一定の難民の実態ではあるものの、すべての難民の経験に当てはまるわけではありません。例えば、ヤセルは違う国へ引っ越さなければいけなかったものの、快適な暮らしを続ける経済力がありました。母親の貯蓄でシリアを離れ、父親がカタールでプロのシェフとして現役で働いて仕送りをしてくれていたので、何不自由なく暮らせたのです。
ヤセルの家族で、海外で働き暮らしていたのは彼の父親だけではありませんでした。日本人の妻と日本に住んでいた叔父がいたのですが、ヤセルの家族がシリアから逃れてエジプトにいることを知り、2人の娘(日本生まれ日本育ちのハーフのヤセルのいとこたち)を連れ、休暇にエジプトに遊びに来たそうです。ヤセルと叔父一家は2ヶ月間大きな家に一緒に住んでのんびり暮らし、カイロでいろいろなケバブを試したりしたと語ってくれました。
すべてが難民の夢のようにうまくいっているように思えました。ヤセルはエジプトの「スラム」地域を離れ、清潔で安全な場所を見つけるという当初の目標を達成し、エジプトでの生活状況にも慣れてきました。しかし、適応の次のステップである同化に踏み出そうとした矢先に、現実が忍び寄ってきたのです。マディナティで安全で清潔な場所を見つけたにもかかわらず、エジプトでの生活は少しも耐えられそうにありませんでした。ヤセルはそこで何もできなかったからです。
ヤセルはエジプトで新しい生活を始めようとしました。エジプトの大学に進学するための願書をダマスカス大学から提出しましたが、不合格となってしまい、仕事を探そうとしましたが、それもうまくいかなかったのです。モルシ前大統領とエルシー前国防相兼軍総司令官のせいだとヤセルは語ります。「モルシに対してクーデターが起きて、エルシーシ大統領へと交代するまでの間、シリアと同じようないろいろなトラブルがあった」そうで、この情勢不安のせいでヤセルはエジプトでほとんど何もすることがなかったのです。「その7カ月間、私たちはただ生き延びてるだけでした」とヤセルは言います。マディナティでの生活状況は望ましいものであったものの、日々生き延びるだけの生活は持ちこたえられるものではありませんでした。「エジプトでは、何もうまくいかなかった。大学も仕事も、自分の将来を継続させるものは何もなかったんだ。」
1.3. 「ここでは何もできないし、未来もない。」
「エジプトでは、何もうまくいかなかった。」
ヤセルは残酷な皮肉に直面しました。父親の経済的援助で買える清潔な住まいを見つけましたが、大学へ行くことも働くことも不可能だったため、生活を始めることができなかったのです。ヤセルと彼の母親は決断せざるを得ませんでした。シリアが安全でなく危機な状況であるにもかかわらず、彼らはシリアに戻る以外に選択肢がなかったのです。
しかし、海外に住むヤセルの家族は、彼らが再び命を危険にさらすことを望みませんでした。 カイロで同居していた叔父は、日本人の妻に彼らの書類を手続きして日本に連れて行くことを相談したいと申し出ました。叔父はすでに自分の家族を日本に呼び寄せる計画を立てていたので、ヤセルの家族が先に来日して日本での難民認定手続きの流れを知ってから、自分の家族を迎えるのが好都合だと考えたのです。
このことが、またしてもヤセルの人生を大きく変えました。彼と母親はエジプトに残るより、戦争中でもシリアに帰る方がいいと決めていましたが、「日本へ来るという神の別の計画があったんだ」といいます。
1.4. 「日本へ来るという神の別の計画があったんだ。」
しかし、難民としての生活は「なぜ」という疑問と先の見えない不安で溢れています。日本へ向かうと決めたヤセルと彼の家族は1~2カ月かけて書類を仕上げましたが、エジプトの日本大使館に何の説明もなく書類の受け取りを拒否されたのです。逃亡を余儀なくされたとき、どんなに準備をしたとしても、新しい生活への順風満帆な旅は保証されません。多くの難民がそうであるように、ヤセルと彼の家族も日本への移住手続きを円滑に進めるために必要なものを揃える努力をしました。しかし、制度そのものが味方についてくれないような時、できることは限られてしまいます。「合法的な書類、エジプトでの居住権、全て揃えていたんだ。居住権だってそのためだけに取得したんだよ。書類には「親族訪問」と書いて、叔父の奥さんの給料や税の明細まで送ってもらって提出したんだ。」と思い出し話してくれました。万全に備えていたのにも関わらず、大使館で書類の受け取りを拒否され「ヨルダンかレバノンに行ってください」と言われてしまったのです。

2. レバノンでの待ち時間
ヤセルはレバノンで過ごした17日間を懐かしく思い出します。エジプトで受け入れられなかった後、日本のビザを申請するという明確な目的を持ってレバノンに入国したヤセルと彼の家族は、そこでの時間が限られていること、ある意味、最後の一頑張りになることを知っていました。
「レバノンにいた2週間は、本当に、本当に、本当に楽しかった。」
ヤセルがレバノンでの滞在をとても楽しかったと覚えているもうひとつの理由は、彼の父親がカタールでの仕事の契約を終えてレバノンにやってきて家族皆と再会し、完全な家族として一緒に過ごせた最後のひとときだったからです。「父は私たちの後にレバノンに来て、それからシリアに戻り、私たちは日本に来た。本当に楽しかった。家族と一緒にその辺をぶらぶらしたりしていただけだけどね。」と彼は振り返ります。
レバノンにいる他のシリア人とは連絡を取っていませんでしたが、レバノン人に温かく迎えられたこともヤセルは覚えています。また、カフェやレストラン、海辺に行き、全然知らない人たちに話しかけたりして楽しんだそうです。

しかし、父親が安定した仕事に就けなくなったことで、お金にまつわる家族の会話は変わりました。エジプトでの快適な住環境とレバノンでの「楽しい」経験とは一転、今や彼らは生活費について深く考えなければならなくなってしまいました。毎月安定した収入から得られるお金がなくなって、限られた貯蓄だけになったからです。
シリアでの生活、エジプトでの生活、そしてレバノンでの2週間から、難民となったあともある程度の暮らしを保てたことが分かります。多くの人は難民を、庇護を求める過程でずっと苦労している人たちと描いており、難民として認められるまでの道のりは皆一緒の一直線なプロセスであると思われがちです。このような描かれ方は、人生の劇的な変化に伴う心の否認をしばしば看過します。彼は素晴らしい人生を送り、うまくやっていました。移転しなければならないからといって、なぜライフスタイルを変えなければならなかったのでしょうか?
しかし、時が経つにつれ、目の前の現実を否定したり無視したりする余地はなくなり、ヤセルは自分の置かれた状況を受け入れざるを得ませんでしたた。貯蓄以外に生活を維持する手段がないため、彼らのライフスタイルは必然的に変わらざるを得なかったのです。ヤセルが経験した最後の 「楽しみ 」はレバノンでのことで、彼の人生は日本での旅に乗り出して一転しました。

3. 日本での道のり
3.1. 「日本での最初の半年間は、人生で最悪の時期だった。」

3.2. 「日本に来たとき、僕たちはゼロだった。何も持ってなかったんだ。」
難民申請の準備として、JARは認定に必要な多くの申請書類の記入を手伝ってくれました。ヤセルは、JARがアラビア語に翻訳された書類を渡してくれたことを思い出します。彼らは叔父が撮った爆撃された家の写真や、母親がシリアの国営テレビで仕事をしていたときの身分証明書、シリアの政治家だった亡命した叔父からのメディアメッセージなども、迫害の証拠として提出しなければなりませんでした。また、具体的な証拠で自分たちの事例をより強固なものにするために、渡邉弁護士と何度も面談しました。ヤセルは、彼らの申請ファイルは「本当に大きかった」と振り返ります。難民申請書類の作成は決して簡単ではありませんでしたが、彼らの迫害を証明するための手段とコネがシリアにあったことが大きな支えとなりましたた。

3.3. 「最初の7カ月は『出てけ』って言われてるようだった。」
10月に来日してから半年後の2014年4月、ヤセルはようやく労働許可を得ました。次項で述べますが、彼は生活のためにさまざまな単純労働を引き受けました。家族を養うために、個人的な目標を一時的に忘れなければならなかったのです。出国当時、彼はシリアの一流大学の学生でした。快適な生活環境にもかかわらずエジプトを離れることを決めたのは、教育も仕事も進められなかったからです。
またも、この劇的なライフスタイルの変化を受け入れるために、状況に適応することを余儀なくされたヤセル。家族の大黒柱として新たな責任を背負わされていました。日本に一緒にいた母親と妹だけでなく、シリアに帰国して職を失っていた父親の分もです。個人的な目標を先延ばしにしてでも、家族を養うことを優先しなければなりませんでした。
家族のために経済的な責任を負わなければならなかっただけでなく、難民認定手続きのための面接を受ける際には、家族の支えとなる必要がありました。ヤセルは、面接は「取り調べ」のようなものだったと振り返ります。「入管の職員が通訳と一緒にテーブルに座って、シリアでの状況について、特に政治や情勢のことを聞いてくるんだ。国に帰ったら危険だって証明しなきゃいけないからね。これが本当に大変だった。簡単なことではないよね。当時の僕はまだ精神的に余裕がなかったから、ただ短い答えを返していただけだった。だから、僕の面接は1日で終わってしまったんだ」と話します。ライフスタイルの変化に適応するために忍耐力を発揮しなければならない中、ヤセルは面接中に苛立ちを感じていたことを認めました。自分がすでに深刻な状況の真っ只中にいることを証明するために細かい質問に答えるよりも、時間を費やすべき「もっといいこと」があるように感じたそうです。強制的に追い出された人生のシナリオをもう一度振り返るよりも、家族のために良い未来を手に入れる方法を見つけるために働いた方がいいと思ったのです。
3.4. 「シリアに戻れば危険だということを証明する必要があった。」

その時点では、シリアに戻ることは事実上不可能でした。ヤセルと家族がシリアに戻れば、彼らは危険にさらされます。しかし、この事実を日本政府に証明するのに長い時間がかかりました。ヤセルが7時間の面接を1回受けただけだったのに対し、彼の母親は20年間シリアの国営テレビで働いていたため、1日がかりの面接を7回も受けなければならなかったのです。
ヤセルは、インタビューが終わるたびに母親が涙を流し、生々しく、辛く、細かい情報を思い出すことを強制されて疲れ果てていたのを覚えています。これが難民に関して見過ごされがちなもうひとつの現実です。新しく生活を始めるためだけに、彼らは人生の困難な瞬間を追体験することを余儀なくされ、一度生き抜くだけでも不公平な経験を何度も振り返えなくてはいけないのです。これは興味深い現実であり、手を差し伸べることを意図しているはずの手続きに人間性があるのか疑問を投げかけます。
3.5. 「7回の面接で母は多くの情報を提供してくれた。難民認定を受けることができたのは、そのおかげだと思う。」
ヤセルは、母親の面接とシリアでの仕事の経歴が彼らのケースに非常に役立ったという事実を十分に認識しています。「母の状況や情報は、文書、会社形態、資料、すべてで証明することができたんだ。政府のために働いていながらその仕事が政府に反対していると知られることで、母が危険にさらされるような話もあった。母はたくさんのことに触れて、自分が危機に直面していることを証明したんだ。」と話します。
1年半にわたる苦労の末、ついに2015年3月、7,586人の申請者の中からその年に認定された他の27人とともに、ヤセルと彼の母親、そして妹が日本で難民として認定されました。
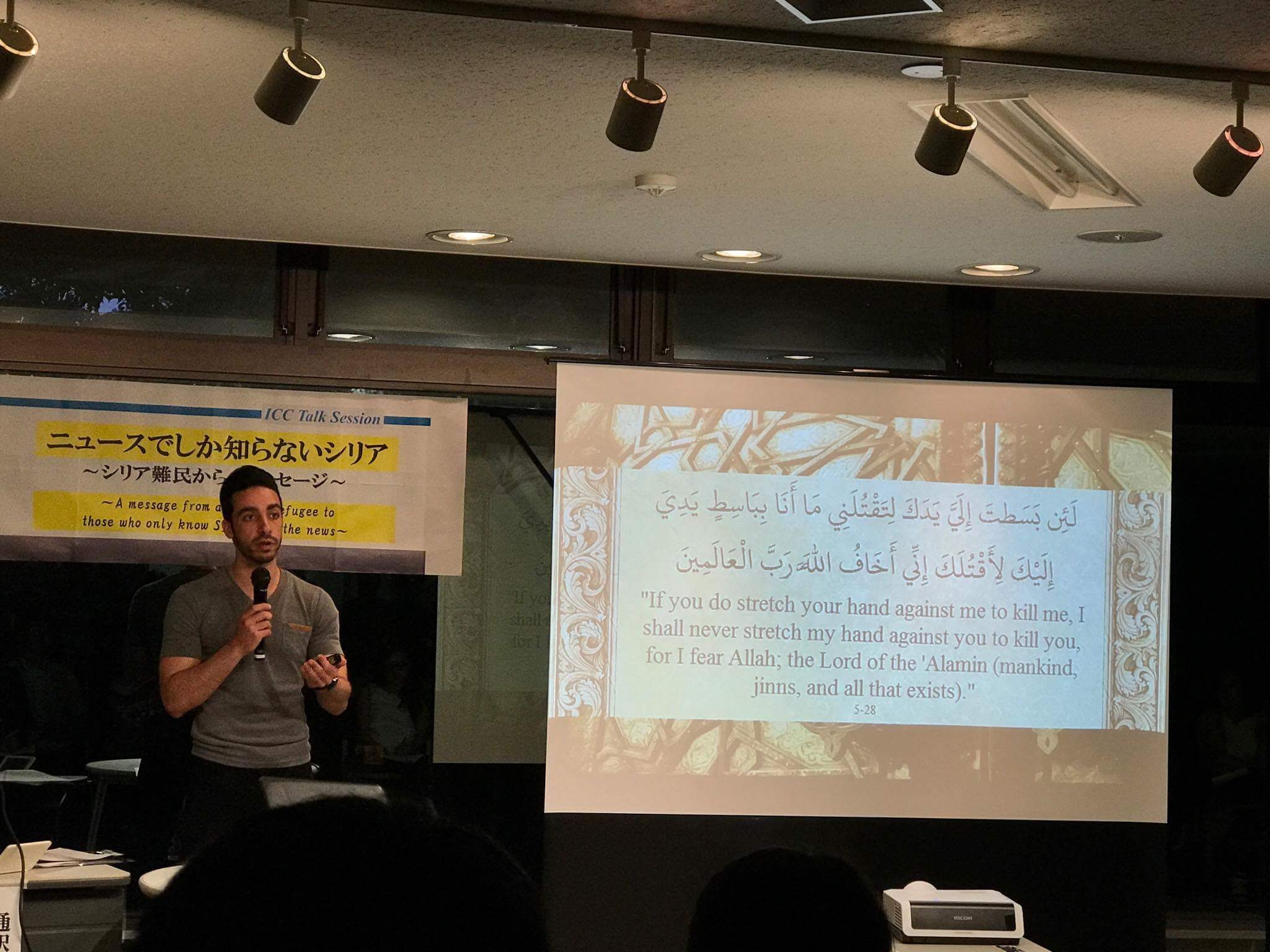
4. 難民認定
難民としての生活にははっきりと分からないことがつきものですが、何よりも確かなのは庇護国で正式に難民として認められることを目指しているということです。それはより良い生活への最終的な保証ではないものの、難民がより少ない制限で新しい生活に適応できるようになることを意味します。ヤセルにとって、日本で難民として認められるというのは、来日当初にできなかった生活を続けられるということでした。健康保険に入れるかどうか、働けるかどうか、勉強できるかどうかわからないという日々の不安の中で苦しむ必要はもはやなくなりました。シリアを逃れてから初めて、ヤセルには自由に生きる権利が与えられたのです。シリアに留まる危険とエジプトでの持続不可能な滞在を乗り越え、ヤセルには日本で新たなチャンスが与えられました。
この新しい人生のチャンスで、ヤセルは物事を学び、やり直さなければなりませんでした。2015年9月、彼は難民事業本部(RHQ)の定住支援プログラムのもとで日本語コースを開始し、1年後には明治大学に奨学金を申請することを決めました。
しかし、2017年4月に明治大学で学生生活をスタートしたときのヤセルは、3年前にダマスカス大学で英文学を学んだヤセルとは違っていました。英文学の代わりにグローバリゼーション、金融サービス、経営学、経済学と専攻を変えることに決めただけでなく、大学での主な目標は自分の未来を築きたいというものに改められたそうです。自分の現在を思い通りにコントロールできるようになったからこそ、自分の未来も確実に想像できるようなったのです。
4.1. 「僕にとって大学とは、ただ腰を落ち着けて自分の将来を築くための時間を与えてくれる場所だった。」
人脈を築き未来に向けた取り組をはじめても、ヤセルは楽しむことも忘れませんでした。大学ではプロフェッショナルなネットワークを作りつつ研究旅行に出かけたりして、ヤセルは世界中の人々と出会っていました。「僕はとても社交的で、人前でスピーチをしても緊張しないんだ。それで学期ごとにやってくる交換留学生のオリエンテーションを担当して、何をすべきかとかあらゆることをアドバイスしていたよ。初日からみんなと仲良くなって、常に新しい人たちと出会うチャンスがあった。他の学生と比べてもっと多くの人と知り合うことができたんだ。」と彼は振り返ります。




多くの難民が自分の身分を明かさない傾向にあることをヤセルは知っています。それは、難民であることがネガティブな意味合いを含んでいると感じ、「安全な側にいたい」と考えるからです。「僕は自分が難民だと言うのを恥ずかしいと思ったことはない。僕は難民で、あれにもなれるし、これにもなれるといった感じだよ。」と話します。
しかし、彼の友人や大学の他の日本人の多くは、シリアや難民の状況について知識がありませんでした。「シリアがどこにあるのか知らない学生にも会った。当時の若い学生、特に日本人学生の多くは『どこ?』って聞くから、『中東ですね。トルコの下ですね。』なんて答えてたよ。その後連絡を取り合うようになってからは、色々質問をされるようになったよ。僕も同じように興味を持ち、授業や宿題のためのプロジェクトを始めたんだ。出身地がどこなのかとか、僕の宗教や難民についてとか、多くの人に興味を持ってもらえたことが嬉しかった。だから本当に楽しかったし、いつでも誰とでも話すことができた」と振り返ります。
難民の実態や、紛争の真っ只中にあるゆえに多くの難民を生み出しているシリアのような国々に対してのこのような認識不足は、日本の難民受け入れ率が低い理由のひとつです。2020年、日本は難民申請者のわずか1.2%しか受け入れませんでした。自ら難民認定手続きに成功したヤセルは、これは政府が難民を必要としていないように見えることが大きな原因だと考えています。
「最初はやっぱり苛立ちを覚えたよ。仕事ができるし、色々できる。なのに受け入れてくれない。若くて体力もあるし、色々したい。言葉だって学びたいのに、そのチャンスを与えてくれないんだ。」
しばしば日本で難民が相手にされないのは、実際には経済移民として日本に滞在しているにもかかわらず、難民であるかのように装って日本にやってくる「偽装難民」と呼ばれる人たちと同一視されているからです。 このような人々の存在によって、日本における難民受け入れの低さを正当化する傾向が多くの人にあります。しかし、日本で難民申請をしている人たちの大半は、実際には逃げるしかなかった人たちであると言っても過言ではありません。
エジプトやレバノンでの不安な経験や、日本での苦難に耐えなければならなかった経験。難民として認められた立場を最大限に活用して、ヤセルは、彼のような難民が新しい居住国で自分の足跡を残そうとベストを尽くしていることを広めたいそうです。彼らは排斥されたり、非難されるべきではありません。新しい生活を始めるように強いられた異常な状況に何とか順応して生きていくために、最善を尽くしているのです。
「僕は難民で、上手くやっている。ベストも尽くしている。この国に住む人たちと何ら変わりはないんだ。」